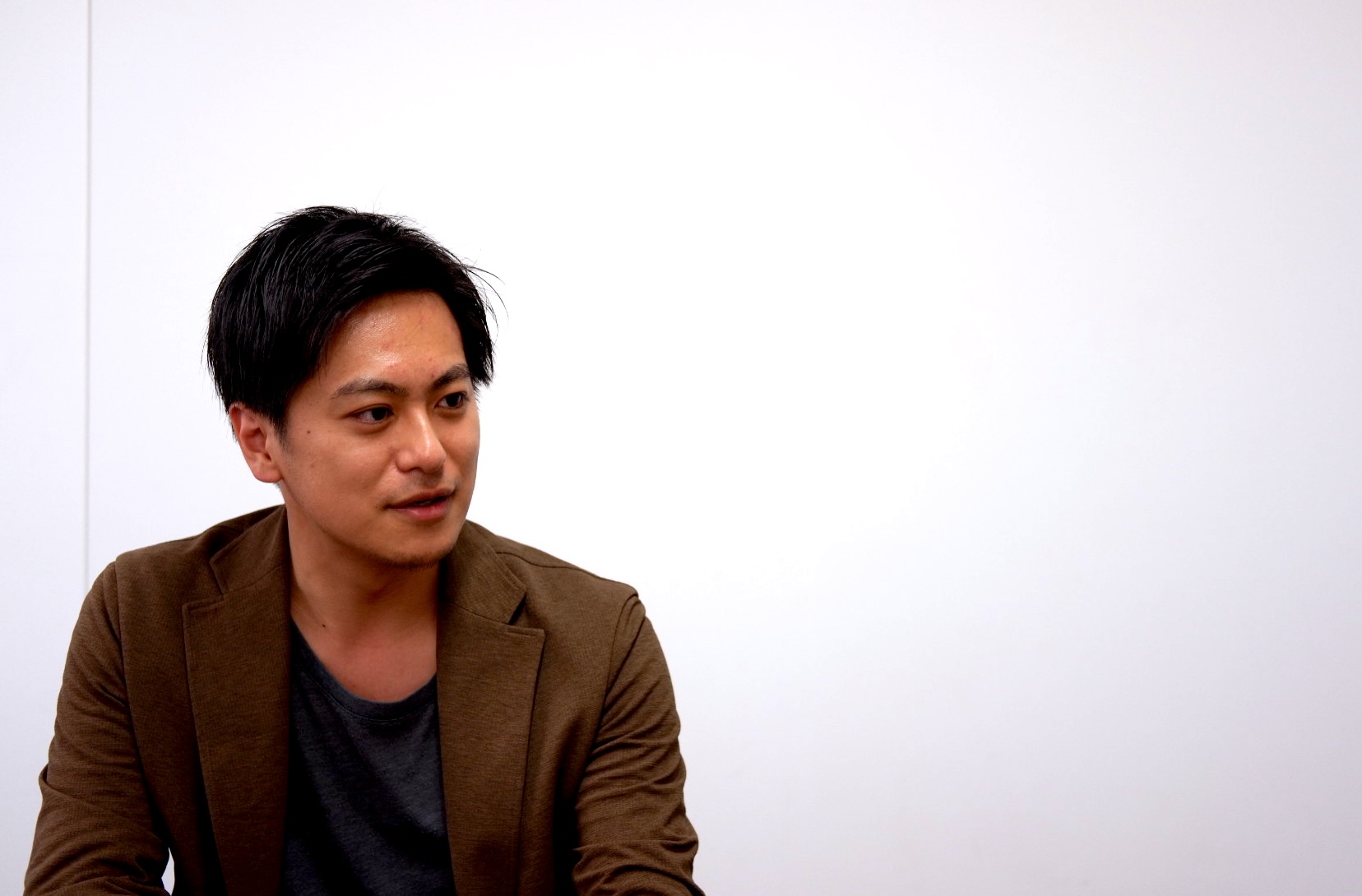「なぜ人類は〇〇するのか?」を考え続ける人

創業開発事業部の田濤 修平は、幼少期をアメリカで過ごした。白人文化の中で異邦人として過ごした経験から「人」に対する関心が強くなった彼は、人に与える食事や営みの影響に興味を抱き、その仕組みを探求するため東京農工大学に入学。博士課程を修めた後にリバネスに入社し、東南アジアで展開しているプロジェクトを中心に様々な仕事に関わっている。彼はなぜリバネスに入社し、何にやりがいを感じているのだろうか?
東京農工大学リーディング大学院一貫制博士課程修了。博士(農学)。専門は有機電解化学。2023年にリバネスに入社し、創業開発事業部に所属。
異国で過ごし、人と向き合った幼少期
–田濤さんは、小さい頃にアメリカに住んでいたそうですね。
はい、父の転勤で、5歳の時にアメリカのオハイオ州に引っ越しました。英語は全く話せなかったので、引っ越し先の近所に住んでいたアメリカ人のバイリンガルの方に半年間英語を教わり、幼稚園に1年通ってから小学校に入りました。
向こうに渡ってから半年間は強い疎外感を感じていました。アメリカには様々な人種が住んでいますが、州によって人種の構成比率が違うんですね。引っ越した先は白人が多い地域で、アジア人はほとんどいなかった。言葉も人種も文化も違う環境の中、周囲からはのけ者扱いされ、「なぜ人は分かり合えないんだろう?分かりあうにはどうすればいいんだろう?」と考えるようになりました。
受け入れてもらうまでには時間がかかりましたが、数年後には誕生日パーティやフットボールに誘ってもらえるようになったんです。その時は嬉しかったですね。言葉も習慣も全く違う土地に行き、受け入れられた経験から、違いがあってもポジティブに解釈することで乗り越えていけることを学びました。
こうした幼少期を過ごし、文化や言葉の違い、そこから生まれるすれ違いなど、「人」にまつわることを考え続けた結果、自分は「人」という存在への関心が強くなったと思います。最終的にアメリカでは7年間を過ごし、12歳の時に日本へ帰国しました。
生物やヒトへの興味から、応用生物科学科へ進学
–日本での中学高校生活を経て、田濤さんはどのような進路を選んだのでしょうか?
生物の授業が好きだったこともあり、東京農工大学農学部の応用生物科学科へ進学しました。
大学で研究したかったのは、生命体としての「ヒト」についてです。自分は小さい頃から「私たちが行動を起こす時、そこにはどのような要因があるのだろう?」と疑問に思っていました。
その答えのひとつが人体にあると思っていて。人は脳を使って情報を処理していますが、情報は電気信号を使って伝達されています。そして、電気信号は体の中で起きる化学反応が生み出している。自分はこうした一連のメカニズムについて研究したかったんです。
このテーマに取り組むため、「有機電解化学」といって、分子間の電子を移動させて医薬品・機能性材料・有機物などを作る学問を学びました。
–有機電解化学は「生命体としての『ヒト』の研究」とは遠い領域に思えます。どうつながるのでしょうか。
少し分かりにくいですよね。まず、有機電解化学は、物質間で起こる電子の交換について研究する学問です。そして、この世界で起きている様々な化学反応は、分子間で電子が交換されることで起きています。
しかし、体の中で起こっている化学反応は膨大なので、全てを理解するためには時間がかかります。そこでアプローチを変えてみました。化学反応の根本となる原理を知れば、「生命体としてのヒト」への理解も深まるだろうと考え、有機化学の研究室に入ったんです。研究室に入ってみると、化学反応は電子の移動によって起こることがわかったので、次は電子について探求したいと思い、電解合成の研究に取り組みました。
研究活動は楽しかったし、自分に向いていると思ったので、そのまま修士・博士一貫課程の、「食料エネルギーシステム科学専攻」に所属して、電子移動の効率を高める研究を進めました。
–研究以外では、大学・大学院時代はどのように過ごしたのでしょうか?
「人」への興味という意味で、人の成長過程や教育にも関心があったので、塾の講師をしていました。また、研究の社会実装に興味があったので、大学の先輩である中村 慎之祐さんが立ち上げたフードテックベンチャー、株式会社グリーンエースの運営にも関わらせてもらいました。この中村さんから紹介されたのがリバネスだったんです。

英語の語学力を活かし、海外事業で経験を積む
–リバネスを知った経緯を、もう少し詳しく教えてもらえますか?
自分はグリーンエースに入社したいと考えていたんですが、慎之祐さんからは「うちにはまだ人を雇うだけの体力がない。田濤がやりたいことをやれそうな会社があるから紹介するよ」と言われたんです。
そうやってリバネスを知ったものの、最初は何をやっている会社か分からなかったので調べてみると、中高生に対する教育事業をやっていて、さらに「科学技術の発展と地球貢献を実現する」というビジョンを掲げていることも知りました。「この会社なら、教育事業を通して人に関われるし、研究の社会実装にも関われるかもしれない」と思い、入社試験を受けたんです。
リバネスでは選考プロセスとして、全社員の前で「入社してから取り組みたいこと」をプレゼンします。自分は「人の成長を促進できる環境と、教育の実践者を育成するための理論を作りたい!」と発表しました。
–入社後はどのような仕事を担当してきましたか?
創業開発事業部に配属されてからは、英語が使えることと、海外の研究の場で発言が聞き入れてもらいやすい博士であることから海外事業にアサインされました。リバネスは、シンガポール、マレーシア、フィリピンに現地法人を構えており、自分は東南アジアでディープテックベンチャーを発掘・育成するエコシステム「TECH PLANTER Southeast Asia」の運営にも関わっています。他にも、リバネス社内の研究チームとして「子どもたちが目を輝かせながら、好きなことをとことん追求できる機会や仕組みを作りたい」という目標を掲げて活動している「教育総合研究センター」のプロジェクトに参加するなど、社内の教育関連事業に参加できるよう動いてきました。

–リバネスで成し遂げたいことや目標はありますか?
今関わっている「ベンチャービルダープログラム」を、事業として大きく育てていきたいです。
研究者やスタートアップが目指す世界観の中には、多くの人にとって非現実的であったり、ビジネスとして広めることが難しいテーマも存在しています。ベンチャービルダーは、このような難しいテーマを、パートナー企業と共に社会実装していく「アントレプレナー」を育てるプログラムです。
アントレプレナーに必要なマインドを指南して、熱意と能力がある人材を輩出できれば、科学技術の発展と地球貢献を実現するための心強い味方になってくれるはず。自身が関心を持ってきた「人」や「教育」にも関係するプロジェクトなので、やりがいを感じています。
異なる専門領域の、異なる視点が面白い
–リバネスで働く中で何に面白さを感じていますか?
毎日なにかしらの「アハ体験」があることですね。様々な研究者と接することが多いので、「こんな着眼点があるんだ!」と驚きがあるんです。
例えば最近、化石の研究者と話しました。その方は恐竜の歯についている傷の研究をされていて、傷を見れば何が原因なのかを判別できるそうなんです。貝殻でついたのか、骨でついたのか、観察すると分かるんだと。思わず「へぇー!」と言ってしまって。
自分はそういった異なる視点を知るのが好きなんです。リバネスは研究者集団なので、全員が異なる専門分野の視点をもっています。さらに、今は海外で展開している事業にも関わっているので、文化や国が異なる研究者の視点にも触れられる。毎日「面白いな」と思いながら仕事をしています。
–最後に、リバネスで実現したいプロジェクトはありますか?
いま熱中しているのが、マレーシアの大学と共同研究しているプロジェクトです。先ほど話した「教育総合研究センター」が進めている「ワクワクについての研究」をベースに、国内外の研究機関や教育機関と連携しながら「興味や関心の定量化」を進めています。
人が何かにワクワクして、モチベーションが高くなっている状態ってあるじゃないですか。子ども達を観察しながら、ワクワクがどのような要因から生まれるのか、どういう条件が重なれば人から人へワクワクが伝わり、巻き込んでいけるのかを研究しているんです。
「ワクワクの定量化」がうまくいけば、ベンチャーの創業期の仲間作りに活用できるでしょうし、研究者が社会実装していく時のパートナー探しにも役立つと思います。入社プレゼンで話した「人の成長を促進できる環境と、教育の実践者を育成するための理論を作りたい!」という構想を実現するために、これからも研究を続けていきます。
◆◇◆リバネスは通年で修士・博士の採用活動を行っています。 詳しくは採用ページをご確認ください。